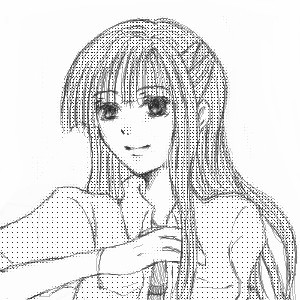-- 貴方に大事な話があるの --
そう言って彼女はとても楽しそうに微笑んだ。
私は彼女のそんな笑顔が大好きで
どうしようもないくらい愛していた。
----------------------------------------------

----------------------------------------------
付き合っていた彼女が居る。
さらりとしたストレートな漆黒の髪。
白い肌と大きな瞳。
彼女の全てを愛していた。
彼女が私の生きる全てだった。
ある日、彼女は大事な話があると言って私を公園へ呼び出す。
何のことなのか検討がつかなくて早く来てくれないかと
ソワソワしていた時に運命のベルがポケットから鳴り響いた。
「はい。」
ブルブルと震えながら私を呼ぶ電話をとり向こうの相手に返事をする。
電話向こうの彼は息を切らしていて慌てた様子で告げてきた。
それこそがまさに悪夢のような一言で力なく手の中の電話は
地面へ音を立てて落ちていった。
「彼女が………死んだ…?」
悪夢ならば覚めてくれと口にする代わりにソレを復唱する。
どうやら交通事故らしい。
急いでいた彼女が突然、飛び出してきたトラックと衝突して
あっさりと私を1人残して逝ってしまったのだ。
病院に駆け込んで既に生きたえている彼女はまるで人形のよう。
「目をあけて下さい……微笑んで下さい……いつものように………」
頬を伝う水は塩の味がした。
私の横には彼女の弟と母が嘆き悲しんでいる。
彼女には父親は居なくて幼馴染の私のことを父親のようだと
親しくしてくれていたけど、私にとってはとても複雑だった。
今となってはそれがどんなに幸せなことだったか。
「……笑って下さい、怒って下さい、悲しんで下さい……」
もう一度、透明な壁を隔てた向こうに居る彼女を見る。
ギリッと歯を食いしばり腕を振り上げると思い切り壁を叩いた。
「俺の名を呼べッ!!」
ふ、と目が覚めたそこは学校の保健室。
重く気だるい体をゆっくりと起こして頭を軽く振る
「夢……ですか。」
夢見が悪かったせいか小さな溜息を落として
ギシッと音を立てながらベッドから足を床へつける。
そうだ。急に気分の悪くなった私は保健室へ来て
保険医の姿が見当たらなかったので勝手に休ませてもらうことにしたんだった。
「今、……何時でしょう…」
「もう放課後ですよ」
誰も居ないと思っていた室内から声が聞こえてビクリと肩を震わす。
あぁ、帰ってきたのかと思考が元に戻ってくれば冷静な判断をし
保険医へ姿を見せるように歩いていく。
「すみません勝手にベッドを使ってしまって」
「いえ、ベッドは病人の為にあるものですから」
そう言った少し冷たい感じのする彼を私は見て軽く微笑む。
初めてみる保険医。漆黒の髪が風に靡いて凄く綺麗だと思った。
自分と同じ男性なのだけれども、まるでそれは……………
それと同時に彼も自分を見てきて目が合う。
「初めまして。……ですね?私は、保険医の霜月日和」
「あ、はい。えぇっと、私は、萩吉乃です」
「………私?」
え?と、小さく声を漏らして首を傾げてみせる。
彼の言った「私」の意味が分からなかったからだ。
「あぁ、いえ。先ほど、寝言で『俺』と言っていたので……」
寝言……というのは、アレ。
どうやら彼にバッチリと聞かれていたようで私は恥ずかしくて
熱を持った顔を隠すように手で覆い下を向く。
「あ、いえ…その……普段は『私』なんです。『俺』はどうしても慣れなくて……」
「そうですか」
放課後と聞いた私はまだ色々と仕事が残っているから、と
逃げるように保健室を出ようとした時。
「『俺の名を呼べ』」
背後から聞こえてきた声に足をピタリと止める。
彼の方を見ずに口を開いてその言葉の意図を確かめた。
「なんですか?」
「いえ、まるで何かの映画のように格好良い台詞だなと。」
「映画……ですか」
そうなら良かったのに。そうだったら、どんなに良かったか。
昔のことは思い出さないようにしていたのに
あの夢のせいと彼の言葉のせいでフラッシュバックしてきた。
人形のように動かない彼女の顔は青白く血が通ってなくて。
名を呼んでも彼女は口を開いて自分の名は呼んでくれなくて。
どんなに泣き叫んでも笑ってくれることはなくて。
ぐっと堪えて戻ってきそうになるモノを手で覆い防ぐ。
室内にある洗面台に急いで走っていき蛇口を捻り水を思い切り出した。
”ジャー”
「げほ……げほ………ぐッ……」
自分の姿を見ていた保険医の彼は微動もせず此方を見ていた。
随分な羞恥を晒していると分かっていても抑えることは出来ない。
「すみません。」
黙っていた彼がそう告げてきた。
「何が……です、か…?」
まだ息苦しい喉を抑え返答する。
タオルがすっと横から出てきてそれを静かに受け取ると水に濡れた部分を拭いた。
ちらりと彼を見上げたら、とても申し訳無さそうな顔で此方を見ている。
言いたいことは何となく分かった。
「嫌なことを思い出させてしまって…」
「いえ。私も、いい加減忘れないといけないんですけどね……」
いつまでもズルズル引き摺っている自分がとても情けない。
自分自身をあざ笑うように声を漏らす。
彼はまた困ったように表情を曇らせ自分は今度こそ保健室を出ようとした。
そうしたら、また声が背後から聞こえてきたのだ。
「忘れたいんですか?」
その言葉に振り返り小さく笑うと
先ほど拭き忘れたのだろうか水が頬を伝う感覚を感じる。
「そんな筈ないでしょう?」
扉を開けて足音が響き渡る廊下を1人歩いていく。
―――吉乃って苗字みたいな名前ね。変なの。
彼女と私は幼馴染で。小さいころからずっと一緒。
―――あのね、クッキー……作ったんだけど甘いもの好き?
彼女の料理は美味しいとは思えないものだったけど、好きだった。
―――好き……なんだけどなぁ。
告白は彼女から。さり気無く公園のブランコに乗りながら呟いてくれた。
「忘れたりしない。貴方を忘れることなんて出来やしない」
目を閉じて貴方の笑い顔を思いだす。
曖昧な昔の記憶の中でも彼女の笑顔だけはハッキリと思い出すことが出来た。
「誰も愛したりしない。貴方以外を愛することなんて出来やしない」
―――あのね、吉乃。貴方に大事な話があるの。
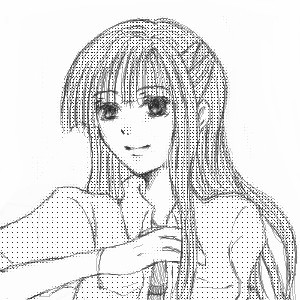
結局、ソレは聞けなかったけど。
END